病院勤務時代から続けてきたニュースレター
「こころのコーヒータイム」の「おまけのクイズ」、
退職・引っ越しで中断していましたが、
障害者就労継続支援B型事業所「人と人」さんのおかげで
無事に再開することができました!(感謝!)
皆さん、お待たせいたしました!
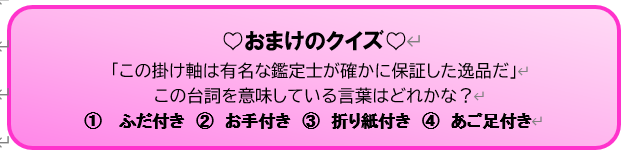
今月号の答えは ③の折り紙付き でした!
若い世代の人たちのなかでは、①を選択することもあるかもしれない、
「鑑定書」を「御札」と連想する、脳みそに柔軟さがあるから。
ではなぜ付けるものが「折り紙」なのか。
そもそも、室町時代の頃までは貴族の贈り物や紹介する人物に
「品質や人柄を保証する」ための文書を添える風習があったそうです。
その文書は二つに折られていて、折り目を下にして文字が書かれていました。
その、折った紙を「折り紙」と読んで、品物や人物に添えて紹介していたようです。
鑑定書とか釣書(身上書)とか…。
そここから、「保障する」という意味で(折り紙がなくても)、
「折り紙付だよ!」などと使われるようになったとのこと。
では、①の「ふだ付き」って?
少し前まで(基い、私が娘の頃まで)よく使われていた言葉。
「あいつはふだ付きのワルだ」。
今ではあまり聞かないけど。
江戸時代は素行が悪くて家から「勘当」された人の人別帳(戸籍謄本みたいなヤツ)に目印を付けて、
「御札」と呼んでいました。
あの時代は、連座制という、今でいうと連帯責任の制度があって、
罪を犯したらその家族や隣人(隣組)も処罰されたそうです。
だから、素行の悪い人が家族にいると、勘当して家族や隣人に影響が及ばないようにしたわけです。
② 「お手つき」
有名な源氏物語でも描写されているカルタ遊び(百人一首)、
私も遠い遠い昔、毎年お正月、10人の従兄弟従姉妹とやったもんです。
この日のために(?)1年を通して暗記してくる勤勉な従姉妹従兄弟たちと違って、
全く努力をしていない(お正月が終わったら忘れている)ふだ付きの私は、
毎年毎年、本番ではかなりの確率で間違った札を叩いていました。
これこそが「お手付き」です。
④の「あご足付き」は昭和世代には懐かしい響き…。
昭和にはこのようなビジネス用語がありました!
「あご」は顎で食事代のこと。
「足」はそのまま交通費のこと。
『この出張は、あご足つきだからラッキーだね』 このように使います。
因みに、「あご足まくら付き」ってのもあって、
これは、もちろん宿泊代も込み込み自社あるいは相手会社持ちってこと。
そんなどんぶり勘定の時代だったわ…。
他にも「一丁目1番地(最優先)」「手弁当(自腹で)」「全員野球(一人残らず)」などなどたくさんあるよ。
お若いの、令和でリピしてください。
ではでは、次回をお楽しみに💞

コメント